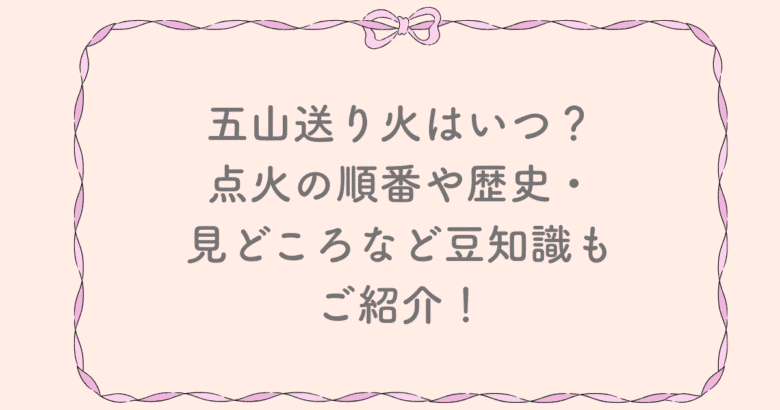京都の夏を締めくくる伝統行事「五山送り火」。
こんな疑問を持つ方も多いのではないでしょうか?
- 五山送り火にはどんな意味があるの?
- 五山送り火はいつ?
- どの順番で灯るの?
この記事では、五山送り火の点火時間の順番や、それぞれの山に込められた意味、あまり知られていない豆知識まで解説していきます。
観覧スポットや注意点も紹介するので、これから五山送り火を見に行こうと思っている方には必見の内容です。
五山送り火の点火の順番と時間を徹底解説
五山送り火は大文字、妙法、船形、左大文字、鳥居形。
それでは、五山それぞれの点火順と特徴について、詳しく紹介していきますね。
大文字送り火:午後8時
五山送り火の中でも最も有名なのが、「大文字送り火」。
毎年8月16日の午後8時ちょうどに、如意ヶ嶽の山肌に「大」の字がくっきりと浮かび上がります。
この「大」の字は縦160メートル、横80メートルもある巨大なもの。
火床と呼ばれる松明が75か所に設けられています。
最も格式が高いとされ、五山の中で最初に点火されることで、他の送り火の始まりを告げる役割も担っています。
京都市内どこからでも見えやすく、鴨川沿いが人気の鑑賞スポットとして知られています。
筆者も、この「大」を初めて見たときの感動は今でも忘れられませんね。
妙法送り火:午後8時05分
続いて点火されるのが「妙法送り火」で、「妙」と「法」の2文字が東山と西山に分かれて灯されます。
これは「南無妙法蓮華経」の「妙」と「法」を意味しており、日蓮宗の教えが背景にあるとされています。
それぞれの点火場所は離れていますが、同じタイミングで灯され、空に文字が浮かび上がるように見えるのが特徴。
点火時間は午後8時05分と、「大文字」の点火からわずか5分後。
静かに、そして神秘的に浮かぶその姿に、毎年見とれてしまう方も多いんですよね。
船形送り火:午後8時10分
三番目に点火されるのが「船形万燈籠送り火」、通称「船形」。
その名の通り、舟の形をした送り火で、祖霊をあの世へ送り出す「乗り物」を表しています。
午後8時10分に、北区の妙見山の斜面で点火。
この送り火は、船の形がしっかり見えるように火床の配置が工夫されています。
左大文字送り火:午後8時15分
次に灯るのは「左大文字送り火」で、午後8時15分に大北山で点火されます。
先ほど紹介した「大文字送り火」と同じ「大」の字ですが、こちらは「左大文字」と呼ばれ、左右対になるように配置されています。
実は、火床の数や配置にも微妙な違いがあって、見比べるのも一つの楽しみ方。
「大」が2つも灯されるのは京都ならではのスケール感ですよね。
ちなみに左大文字は、視界が開けた高台やホテルの上階などから見るのがオススメです!
鳥居形送り火:午後8時20分
最後に点火されるのが「鳥居形松明送り火」。
午後8時20分に嵯峨曼荼羅山で灯され、五山送り火の締めくくりを飾ります。
鳥居の形を模した火床は神聖さを感じさせ、その名の通り、祖霊が神の世界へ帰るための「門」の意味を持つといわれています。
他の送り火よりも太く力強い火が特徴で、松明が焚かれる様子は迫力満点です!
嵯峨嵐山エリアは自然が多く、観光ついでに見るのにもぴったりなスポットですよ。
五山送り火とは?意味や歴史を知ろう
五山送り火とはどんな意味があるのか、ルーツや歴史などから見ていきましょう!
送り火の意味とは
「送り火」とは、お盆に帰ってきたご先祖様の霊(精霊=しょうりょう)を、あの世へ送り届けるための火のこと。
「迎え火」で迎えた精霊を、今度は送り火によって浄土へと送り返す—これが日本古来の祖霊信仰と仏教の習合によって生まれた風習です。
五山送り火は、その送り火の中でも特に大規模かつ象徴的なものとして、京都の人々の信仰に深く根付いています。
ご先祖様への「ありがとう」と「また来年会いましょうね」の気持ちを込めた祈りの火でもあるんですよね。
私も毎年この行事に触れるたび、心がじんわり温まります。
起源は室町時代とも言われる
五山送り火のはじまりについては諸説ありますが、文献として確認できるのは室町時代以降とされています。
とはいえ、それよりも前の鎌倉時代や平安時代にルーツがあるという説もあり、詳細ははっきりしていません。
なぜ記録が少ないのかというと、もともとこれは政治的な儀式ではなく、あくまで「地元の信仰行事」だったからです。
村人たちが自然と始め、口伝で受け継がれてきたため、公式な記録がほとんど残っていないんですね。
それだけに、「人の手と心で守られてきた」ということが素敵ですね。
五山の由来と広がり
「五山送り火」という名前は、点火される5つの山を意味しています。
具体的には、「大文字(如意ヶ嶽)」「妙法(松ヶ崎の2山)」「船形(妙見山)」「左大文字(大北山)」「鳥居形(曼荼羅山)」の5つ。
それぞれに異なる意味や信仰が込められています。
この五山の範囲は、京都市内をぐるりと取り囲むように分布していて、それぞれの地域で独自に保存会が活動しています。
地域の人たちが「自分たちの山は自分たちが守る!」という誇りをもって継承しているのが伝わってきますね。
江戸時代の「幻の送り火」
実は、現在の五山以外にもかつては多くの送り火が存在しました。
江戸時代には、左京区市原野の「い」、右京区鳴滝の「一」、西京区西山の「竹の先に鈴」、右京区北嵯峨の「蛇」、観音寺の「長刀」などもあったといわれています。
しかし、これらは時代とともに消え、今ではその記録だけが残されています。
もしそれらも含めて続いていたら、「七山送り火」や「十山送り火」になっていたかもしれませんね。
そんな幻の送り火たちにも想いを馳せながら、今の五山を観るとまた違った見方ができるかもしれません。
五山送り火の見どころと楽しみ方
五山送り火の見どころと楽しみ方について解説していきます。
その魅力、もっと深堀りしていきましょう~!
①各山ごとの個性ある形
五山送り火の魅力のひとつは、それぞれの山が持つ個性的な形です。
「大文字」は誰もが知る王道の「大」の字で、遠くからでもすぐにわかる力強さがあります。
「妙法」は妙と法の2文字が並ぶユニークな組み合わせ。「あれ?2か所あるぞ?」と気づくと感動します。
「船形」はまるで空を旅するようなシルエットで、見る人の想像力を掻き立てます。
「左大文字」は、右側の「大文字」とのシンメトリーで、一緒に見られると感動倍増!
「鳥居形」はその名の通り、神聖な鳥居を象ったフォルムで、フィナーレを彩るにふさわしい荘厳さ。
どれも意味があり、形にもストーリーがあるので、見る前にちょっと調べておくと、数倍楽しめますよ!
②ライトダウンと火の対比
京都市では、送り火の時間に合わせて「ライトダウン(ネオンや広告灯の消灯)」を実施しています。
これがまた最高に美しい!街の光が落ち、静寂に包まれた中、火文字が夜空に浮かび上がる瞬間は鳥肌もの。
写真ではなかなか再現できない空気感なを感じられるので、現地でぜひ体感してほしいです。
実は知られていない五山送り火の豆知識
実はあまり知られていない五山送り火の豆知識について、紹介していきます。
見ているだけではわからない、裏側も知れば、五山送り火にもっと興味が湧くかもしれませんね!
すべて手作業で点火
実は五山送り火の点火は、今でもすべて手作業で行われています。
各山の保存会の方々が、何日も前から火床(ひどこ)と呼ばれる場所に松明を並べ、当日は人力で火をつけていきます。
特に「大文字」は火床の数が75か所もあり、それぞれに人が配置されて、一斉に点火をスタートします。
ドローンや自動点火装置ではなく、あえて「人の手」で行うことにこだわる理由は、「送り火は信仰と祈り」だから。
その真剣な表情や手際の良さは、まさに職人技!見えないところで支える人たちに、心からの敬意を送りたいですね。
保存会の努力と誇り
各山には「保存会」と呼ばれる地域団体があり、1年を通して準備・整備を行っています。
この活動はボランティアが中心で、地元住民の方が代々受け継いでいるんですよ。
火床の修繕、資材の調達、安全確認、観覧ルールの整備など、仕事は多岐に渡ります。
送り火が灯るたった30分のために、何十時間、何百時間という時間がかけられている…。
これを知ると、見る側としても姿勢が変わりますよね。静かに、敬意をもって観覧したいものです。
火床の構造にも注目
火床は、ただ松明を置いただけのように見えるかもしれませんが、実はとても緻密な構造になっています。
例えば、大文字の火床は鉄製の枠で支えられ、中に杉や松の割木が組まれています。
湿気や雨に備えてビニールシートで覆われることもあり、天候対策もばっちりです。
また、火がスムーズに立ち上がるように風の流れまで計算して配置しているとか…!
伝統と現代の融合
近年では、伝統を守りつつ「現代技術の活用」も少しずつ進んでいます。
例えば、保存会の一部では点火の順序確認やタイミング調整に無線機を活用したり、安全管理にドローン映像(あくまで事前の下見)を利用することもあるそうです。
点火の瞬間をインターネットでライブ配信する取り組みも始まり、現地に行けない人にも感動を届けてくれるようになりました。
こうした取り組みは、次世代に行事を伝えていくうえで大きな役割を果たしています。
変わらない部分と、時代に合わせて変えていく部分。まさに伝統と革新のバランスが感じられますね。
まとめ|五山送り火の順番と意味を知って心に残る夜を
今回は五山送り火について豆知識などを解説してきました。
五山送り火は、京都の夏の夜空を照らす伝統行事であり、ご先祖様を送る祈りの火でもあります。
ただ見るだけでなく、その意味や歴史、裏側にある努力を知ることで、送り火の持つ深い価値が見えてきます。
心静かに夜空を見上げると、五山送り火を目に焼き付けましょう。