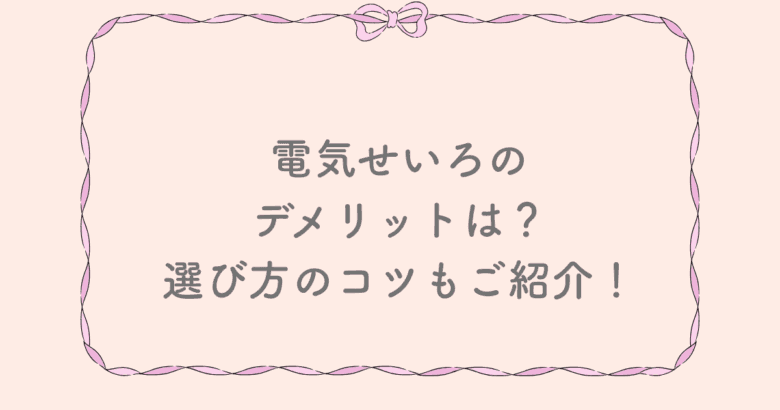ほったらかしのまま蒸し料理ができる電気せいろ。
あったらいいなと思いつつも、こんなお悩みはありませんか?
- 電気せいろのデメリットが気になって、なかなか購入に踏み切れない
- せいろの手入れが面倒に思えて、迷う
- 欲しいけど、使い方が難しそうで心配
この記事では、電気せいろのデメリットをお伝えします。
- 収納場所を取る
- 揚げる・炒める調理はできない
- せいろの手入れが面倒
- ガス火のせいろに比べて、蒸し時間が長くなりがち
- せいろの香りが食材にうつることがある
また、デメリットをカバーする電気せいろの選び方や実際のおすすめ商品も詳しくご紹介していきます。
電気せいろの5つのデメリット
電気せいろのデメリットを詳しく見ていきましょう!
収納場所を取る

引用画像:楽天市場
電気せいろは炊飯器ほどの大きさがあり、思ったよりも場所をとります。
しかも、せいろは2段、3段と高さがあるので、あらかじめ置くスペースも必要ですね。
また、使わないときに、本体、せいろ、トレー、ふたや筒など一式を収納しておくスペースも確保できかどうかもポイントです。
揚げる・炒める調理ができない
電気せいろでは揚げたり、炒めたりする調理ができません。
あくまでも蒸し料理を作るためのもの。
ヘルシー料理のレパートリーは広がりますが、唐揚げや天ぷらなどはできないので、注意しましょう。
せいろの手入れが面倒

引用画像:楽天市場
蒸し料理は水分が多いので、使用後部水タンク、トレイ、フタ、せいろ本体など、洗い物が増えがちです。
せいろは布で拭いたあと、しっかり乾かさないと、カビやにおいの原因になることも。
中には、食洗機NGのモデルもあるので、注意しましょう。
蒸し時間が長くなりがち

引用画像:楽天市場
電気せいろで作る蒸し料理はガス火のせいろに比べると調理時間がかかります。
特に、大きめの塊肉や大きい食材だと、完全に蒸されるまでに時間がかかることもあるので、注意しましょう
加熱パワーやサイズの面で、どうしてもガスせいろにはかないません。
大きなシュウマイや、蒸しパン、ファミリー用の中華まんをたくさん作りたいときは、容量や火力に物足りなさを感じてしまうこともある方も
香りが食材にうつることがある
竹製と杉製のせいろの場合、出来上がった時に蒸気が出て、杉の良い香りがします。
特に、杉製のせいろの香りがうつりやすい傾向にあります。
この香りがいいと思う方もいますが、逆にこれは合わないと感じる方もいますので、気をつけましょう。
電気せいろの5つのメリット
電気せいろのメリットをご紹介します。
手軽に使える

引用画像:楽天市場
電気せいろの大きな強みは「とにかく手軽に使える」ということです。
ガス火のせいろだと、コンロの場所を空けたり、火加減を気にしたり、いろいろ気を遣います。
電気せいろなら水と食材を入れてスイッチを押せば、あとはほったらかしでOK。
朝ごはんやお弁当準備の時短にもなるし、料理が苦手な人や料理初心者でも失敗しにくいから。
カロリーが抑えられて、ヘルシー

引用画像:楽天市場
蒸し料理はとにかく低カロリーでヘルシー。
電気せいろは食材の水分を保ったまま加熱できるのが特徴。
野菜は蒸すことによって、甘みが出ますし、冷凍のシュウマイや肉まんもふわっと蒸し上がります。
特に、野菜をたくさん食べたい健康志向の方におすすめです。
タイマーや自動オフが便利

引用画像:楽天市場
タイマーや自動オフ機能があるのも電気せいろの魅力。
ガスせいろの場合は火加減をチェックしいないといけないですが、電気せいろなら出来上がったら自動でOFFする機能がついています。
これが本当に便利で、食材をセットしてタイマーを回しておけば、うっかり忘れても焦げたりしません。
火を使わないので安心
電気せいろは火を使わないので、うっかり火をつけっぱなしということもありません。
火加減を見張る必要がなく、水を入れてセットしたら放っておける手軽さが魅力ですね。
「ごはんの準備にかける時間を減らしたい」「他の家事や仕事をしながら調理したい」人には本当に便利なスグレモノです!
せいろのまま蒸し料理を出すと華やかに見える

引用画像:楽天市場
出来上がった蒸し料理は、せいろのまま食卓に出すこともできます。
温野菜、肉まん、シュウマイなど蒸し料理のバリエーションは豊富。
蒸気に包まれて、このような蒸し料理をせいろのまま食べられると、自宅にいながらレストラン気分が味わえますね。
電気せいろのデメリットをカバーする選び方
「せっかく買うなら失敗したくない!」という方のために、デメリットをカバーする選び方と使い方のコツを徹底解説しますね。
①収納場所が気になる方はコンパクトサイズを選ぶ
ある程度の場所を取るので、収納場所が気になる方はとにかくコンパクトサイズを選びましょう。
一人暮らし・少人数向けの容量1.5L~2L程度のコンパクトモデルがおすすめ。
卓上で手軽に使えるし、収納場所にも困りません。
せいろを使わない日は卓上鍋にもなりますよ!
調理時間が気になる方はワット数をチェック
蒸しあがりの速さや食材の仕上がりを重視したい方は、「ワット数(出力)」に注目しましょう。
電気せいろのパワーはモデルごとに大きく差があります。
400W程度だと加熱に時間がかかりやすく、800W以上あるとガス火に近い加熱力を感じられます。
また、容量が大きくなるほどパワーも必要なので、家族用や多めに蒸したい場合は、出力が高いモデルを選ぶのがおすすめです。
火力は100〜300Wの保温モードから、最大1000Wまで、6段階に調節できるから、弱火から強火の料理まで楽しめます!
お手入れが気になる方は外しやすい設計のものを選ぶ
「お手入れが面倒そう…」という方は、パーツの少なさや洗いやすさを重視して選ぶのがポイントです。
本体と受け皿、せいろやフタなどが取り外しやすくて、シンプルな構造のモデルを選べば、グッと使いやすくなります。
最近は「丸洗いOK」や「抗菌加工」など、衛生面にこだわったモデルも増えてきました。
洗い物が多くて挫折しがちな人こそ、ラクできる設計かどうか事前にチェックしてくださいね。
蒸し鍋は本体から外して洗えるので、使いやすいです♪
まとめ|電気せいろのデメリットと選び方のコツを徹底解説
今回は電気せいろのデメリット、メリット、選び方のコツなどをご紹介してきました。
- 収納場所を取る
- 揚げる・炒める調理はできない
- せいろの手入れが面倒
- ガス火のせいろに比べて、蒸し時間が長くなりがち
- せいろの香りが食材にうつることがある
一方で、手軽に使える・タイマー機能で放置OK・火を使わない安心感など、便利なポイントもたくさん。
自分の使い方やライフスタイルに合わせて、選ぶことが大切です。
ぜひこの記事を参考にして、お家に居ながらにして本格的な蒸し料理を楽しみましょう!